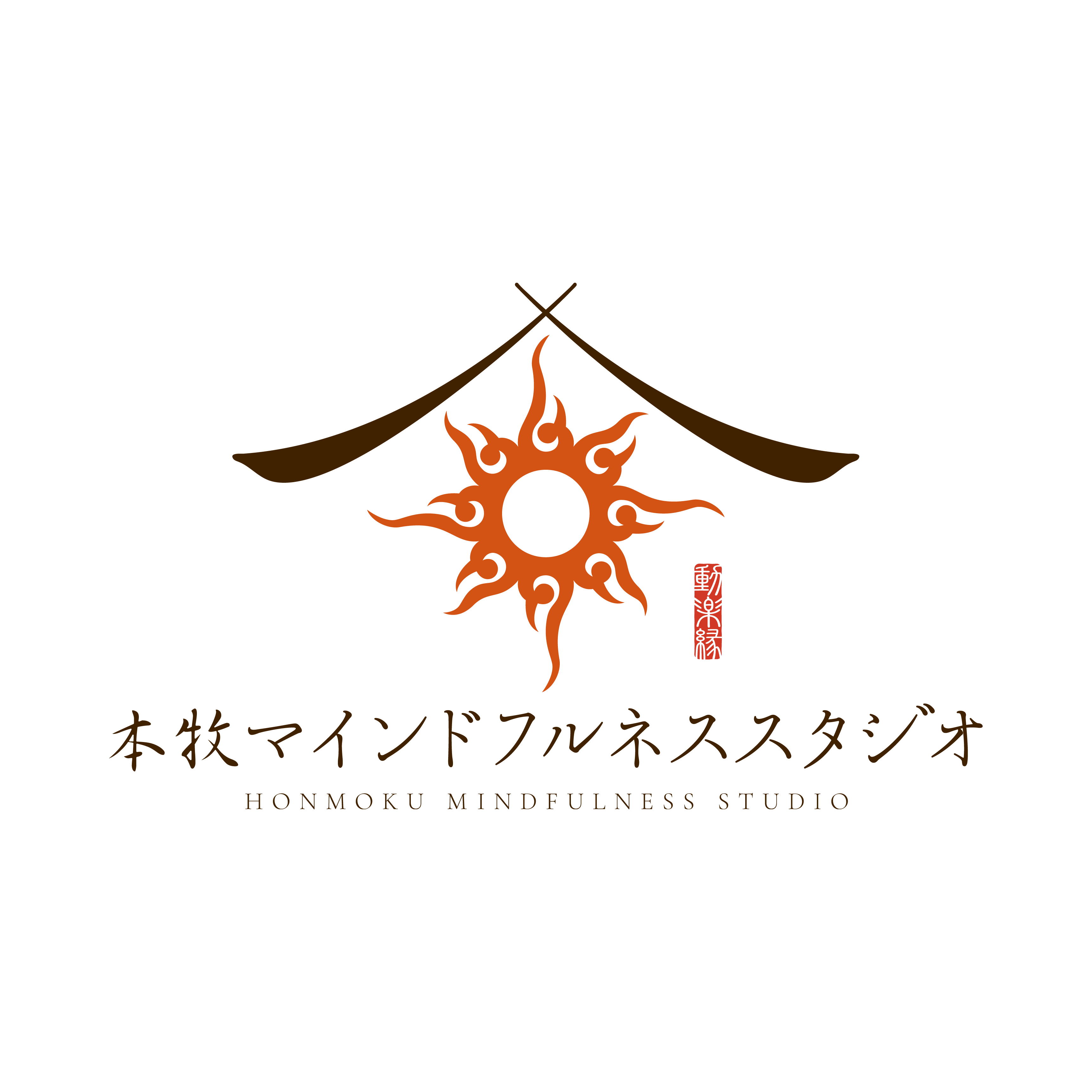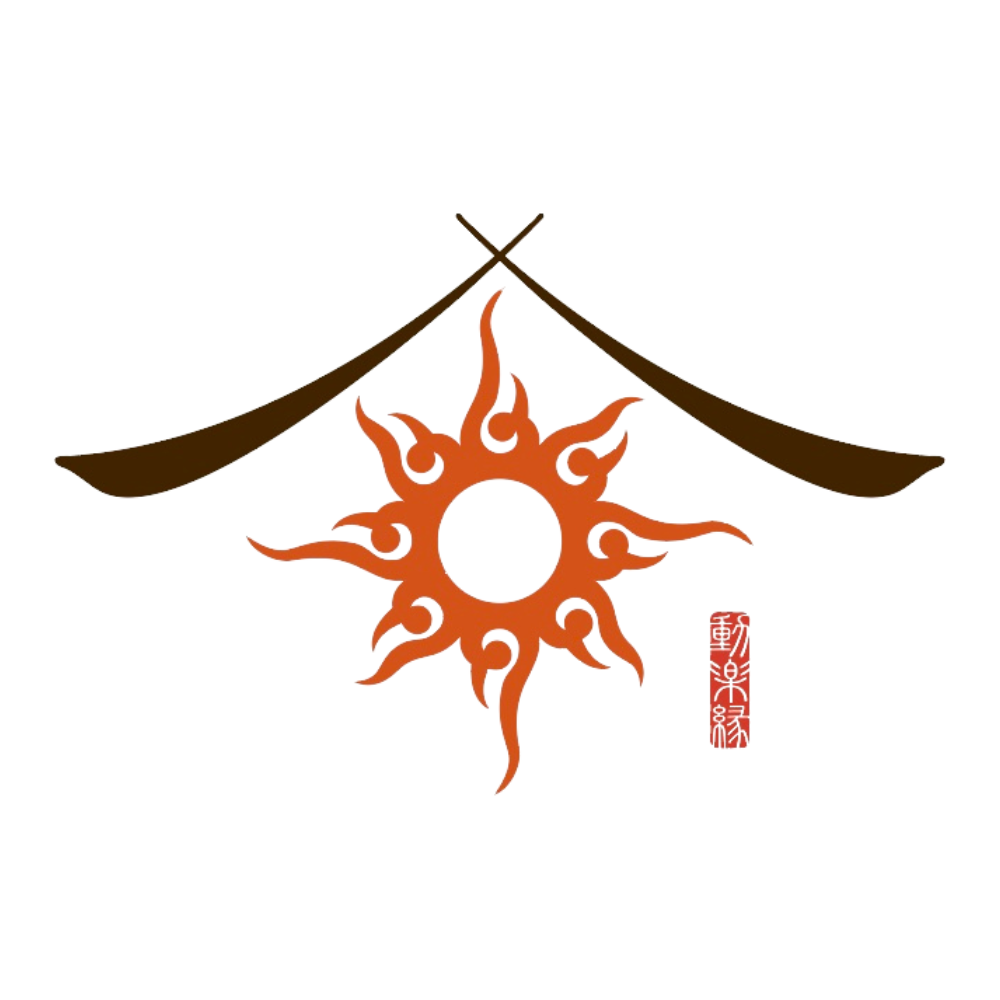
PROGRAM
プログラム紹介
マインドフルネスプログラムの流れ
STEP1
現在の脳疲労の具合を知る
⽇々の様々な情報、⼈間関係、睡眠の質によって、現時点での脳疲労の具合をチェックリストでチェックをしていきます。脳の疲れは、⼼の病の原因にもなりかねません。最初のステップでご⾃⾝の疲れがどれくらいなのかを認識するだけで、既に疲れは改善する⽅向に向かっています。

STEP2
⾃分の⼼を知る
脳の疲労のみでなく、⼼が弱くなっていないかご⾃⾝の状態を知ることにしましょう。⽇本⼈は元々⾃⼰肯定感が低いと⾔われております。
マインドフルネによって、ありのままの⾃分を⼤切にする「⾃慈⼼」を⾝につけていきます。この⾃慈⼼を育む上で「⾃分への優しさを持つ」「完璧主義にならない」「瞬間瞬間を⼤切にする」ことを意識していきます。

STEP3
マインドフルネスの効果を知る
〜仕事編〜
企業やビジネスパーソンがマインドフルネスに注⽬をして、企業研修などで取り⼊れている理由は「仕事のスピードの向上」「プレゼン⼒の向上」「マネジメント⼒の向上」「創造⼒の向上」「ストレス耐性の向上」などに繋がるからであります。その理由としてマインドフルネスを実践することで脳内に以下の7つの変化が⽣じるからであります。
①CEN(セントラル・エグゼクティブ・ネットワーク)を担う脳の部位が活性化する
②SN(セイリエンス・ネットワーク)を担う脳の部位が活性化する
③CEN とSN の結合が固まる
④DMN(デフォルト・モード・ネットワーク)を担う脳の部位の過活動が収まる
⑤記憶や感情を司る海⾺が⼤きくなる
⑥不安や恐怖に反応する扁桃体が⼩さくなる
⑦⼈の気持ちに敏感になり、援助や⽀援に対して積極的に⾏動するようになる右内側前頭眼窩⽪質が活性化する。
という効果が現れます。

STEP4
マインドフルネスの効果を知る〜⼈間関係編〜
円滑な⼈間関係を築く上で⼤切なのが「セイリエンス・ネットワーク(SN)」であります。このセイリエンス・ネットワーク(SN)を活性化させる為にはマインドフルネスがとても有効的であります。外の環境から受ける刺激や情報に対して適切な思考や⾏動を取るために司令官の役割を担っているセイリエンス・ネットワーク(SN)はこの他に⼤切な役割も担っています。
それは「不安・怒り」に対して落ち着かせる作⽤であります。また、このセイリエンス・ネットワークを活性化することによって⾃他の「悲しみ、寂しさ、悔しさ」などの⼼の繊細な変化に気づくことが出来て、相⼿の気持ちが理解できて優しさや温かい⾔葉掛けが出来るようになり、良好な⼈間関係を築き上げることが可能となります。

STEP5
マインドフルな思考法をマスターする
マインドフルネスは実践に⼊る前に思考法を理解することが⾮常に⼤切だと⾔われております。なぜなら、マインドフルネスの思考法を正しく理解できていないで実践するとゴールを誤ってしまう可能性があるからであります。マインドフルネスの具体的な思考法は①気づく②⼿放す③集中する。の3つのステップで成り⽴っています。
「①気づく」の段階では、⾃分の中に浮かんできた思考は、過去の経験を思考習慣によるものだと気付きます。
「②⼿放す」の段階では、過去の経験や思考習慣によって作られた雑念を⼿放します。
「③集中する」の段階では、いまこの瞬間に集中していきます。
「①気づく」の段階における考え⽅の習慣を、認知⼼理学では「⾃動思考」と呼びます。この⾃動思考は、嫌なことに出会した時に⾃然と浮かぶ思考のことであります。これがネガティブだったり、歪んだ思考になると同じ出来事を経験したとしても捉え⽅が全く異なってきます。
例えば、仕事場で同じミスをしたとしても上司と先輩では全く違う反応になるケースもあるかと思います。上司は優しく対応してくれているのに、先輩はものすごく怒っている場合、先輩の⾃動思考はネガティブな⽅向に歪んでいることで怒られた側も⾃⼰否定に繋がる⾃動思考になってしまいます。ネガティブな⾃動思考を修正・再構築をすることで「気分」や「⾏動」が変わってきます。

STEP6
マインドフルな思考法①「気づく」
マインドフルな思考法の第⼀段階が「気づく」であります。何か不快な出来事に対してネガティブに解釈してしまうと「気分が落ち込む」「周囲の⼈と争うような⾏動」をしてしまいがちです。それによって、様々な⼼の病気になりやすくなります。根本的な思考を変えない限り、⾃動思考はいつまでもネガティブのままになってしまいます。
マインドフルな思考法では、歪んだ思考に気付き、それを⼿放すことから開始します。
歪んだ思考法とは「完璧主義思考」「⾃⼰嫌悪思考」「ネガティブ思考」「感情的思考」などが存在します。これらの思考が⼼に浮かんだときは認知⾏動療法を使って改善していきます。

STEP7
マインドフルネ思考法②「手放す」
マインドフルな思考法の次のステップは「手放す」大切さを習得します。人は「考えてはいけない」と頭の中で意識すると、ついつい考えてしまうものです。心理学には「思考抑制の逆説的効果」というものがあります。例えば「りんごのことは60秒間絶対に考えないでください」と言われると、人の頭の中では逆にりんごのことばかり考えてしまいます。
これを仕事で大事なプレゼンの場面で以前失敗の経験があって、「今度こそは失敗しないようにしよう」と自分に言い聞かせるとかえって失敗を意識して緊張が高まってしまいます。
マインドフルネスのプログラムでも同じであり、瞑想中に「余計なことを考えないようにしよう」と意識をすると、かえって雑念が多く頭に浮かび瞑想に集中できなくなります。これを逆説に意識することが「意識しても大丈夫」「考えていい」と自分を許すことがとても大切であります。許したあとは手放す(川に流す)「葉っぱ瞑想法」がとても大切であります。

STEP8
マインドフルネ思考法③「集中する」
マインドフルネスの最後の思考法は「集中する」です。雑念を手放したあとは目の前のことに集中できるように、シンプルに目の前のことに意識を向けることが大切であります。例えば、仕事上のトラブルがあった時に気持ちが動揺していることを認めたあとは、その気持ちを手放して、ただ目の前のやるべき課題に集中していくことで、あとになって「ものすごく集中していた」ことに気が付きます。マインフルネスな心の状態を取り戻すことが可能となります。
ただし、「マインドフルネスな心の状態にしよう」という目標を立ててしまうと、その目標自体が「雑念」となってしまいます。多くの自己啓発本には「目標を持つ大切さ」が書かれおります。目標を持つことは確かに大切でありますが、例えば野球のバッターがホームランを打とうとする目標を持つと、それ自体に力みに繋がりホームランを打つどころかボールに当たらないケースが多くなります。それよりも、目の前のボールに集中してボールにバットを当てていく方が良い結果に繋がる事が多いのではないでしょうか。過去も未来ではなく今現在、目の前のことに集中していくことが当スタジオが目指しているマインドフルネスプログラムであります。


プログラム料金
よくある質問
-
瞑想の効果はどのように実感できますか?
-
瞑想の効果を得ようと意識し過ぎてしまうと、瞑想に注意を向けることが難しくなりがちなので、あまり効果を気にしないで日々習慣にすることをお勧めします。実際には、「イライラすることが少なくなった」「心が動揺するような出来事があっても、比較的穏やかに受け止められるようになった」「自分にも他の人にも、優しい気持ちを持てるようになった」といった変化に気づかれる方がいらっしゃいます。
-
瞑想を続けるコツはありますか?
-
毎日の決まった時間、あるいは決まった行為のタイミングで瞑想をルーティンにするのがお勧めです。たとえば「起床したら最初に数分間の呼吸瞑想をする」「朝の通勤中は歩く瞑想を意識する」「昼休みが終わって仕事を始める前に必ず呼吸瞑想」「夜寝る前にベッドの中でボディスキャン瞑想」といった具合に、ご自身の取り入れやすい機会を見つけてみて下さい。
-
一日のどの時間帯に瞑想するのが良いですか?
-
時間帯による瞑想の効果に違いがあるかどうかについては、明らかになっていません。これは人それぞれライフスタイルが異なることが一つの理由と考えられます。ご自身にとって、もっとも心地よく瞑想できるタイミングを見つけてみるつもりで、色々と試していただければ幸いです。